給与
初任給額
| 職種 | 区分および初任給額(地域手当含む) | |||
|---|---|---|---|---|
| 事務職 (学芸員・司書含む) |
大学卒 271,040円 | 短大卒 259,840円 | 高校卒 245,728円 | 中学卒 224,336円 |
| 技術職 社会福祉職 |
大学卒 271,040円 | 短大卒 259,840円 | 高校卒 245,728円 | - |
| 保育教諭 | 大学卒 271,040円 | 短大卒 259,840円 | - | - |
| 心理職 | 283,472円 | - | - | - |
| 技能職 | 246,736円 | - | - | - |
| 保健師 | 277,200円 | - | - | - |
| 看護師 | 大学卒 277,200円 | 短大・専門3卒 271,040円 |
短大2卒 267,344円 |
- |
| 獣医師 | 303,632円 | - | - | - |
| 薬剤師 | 大学6卒 303,632円 | 大学卒 290,192円 | - | - |
| 管理栄養士 診療放射線技師 臨床検査技師 理学療法士 作業療法士 言語聴覚士 |
大学卒 290,192円 | 短大卒 274,288円 | - | - |
モデル給与額
| 期間(目安) | 月額 |
年額 (※期末・勤勉手当含む) |
|---|---|---|
|
【主事昇格時】 大学卒入庁6年目 短大卒入庁後8年目 高校卒入庁後10年目 |
309,456円 | 5,224,387円 |
|
【係長級昇格時】 大学卒入庁11年目 短大卒入庁後13年目 高校卒入庁後15年目 |
346,976円 | 5,938,491円 |
※上記額は令和8年1月1日現在における金額です。
主な手当等
| 手当名 | 説明 | 支給額 |
|---|---|---|
| 期末・勤勉手当 | 民間におけるボーナス・賞与等に相当する手当。 6月と12月の年2回支給されます。 |
給料の4.65月分(年間合計) (採用初年度の場合は勤務期間によって異なります。) |
| 扶養手当 | 扶養親族のある職員に支給されます。 | 配偶者等:3,000円/月 子:11,500円/月 |
| 住居手当 | 借家または借間に居住し、家賃を支払っている職員に支給されます。 | 市内居住:上限31,000円/月 市外居住:上限28,000円/月 |
| 通勤手当 | 通勤のため、交通機関等を利用してその運賃等を負担することを常例とする職員及び自転車等を使用することを常例とする職員に支給されます。(片道2km以上) | 公共交通機関:上限150,000円/月 自転車等:上限11,300円/月 |
※上記額は令和8年1月1日現在における金額です。
※その他手当についても支給要件に応じた額が支給されます。
昇給
1年に1回、勤務実績に応じて行います。
勤務条件
勤務時間/休日
・勤務時間:原則、月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分
・休憩時間:原則、午後0時から午後0時45分
・休日:原則、土曜日・日曜日・祝日および年末年始(12月29日から1月3日)
※配属先により異なる場合があります。
休暇等
| 休暇名 | 概要 | 日数 |
|---|---|---|
| 年次有給休暇 | - | 年間20日 |
| 夏季休暇 | 7月1日から9月30日までの間に取得できる休暇 | 6日 |
| 通勤時間 | 妊娠中の職員の通勤による負担軽減を図るための休暇 | 1日1時間以内 |
| 不妊治療休暇 | 不妊治療を受ける場合に取得できる休暇 | 有給5日(体外受精等の不妊治療の場合は10日) 無給6日 |
| 生理休暇 | 生理日に勤務することが著しく困難な場合に取得できる休暇 | 1回2日 |
| 妊娠障害休暇 | 妊娠中の女性職員が妊娠障害(つわり)のため勤務することが著しく困難な場合に取得できる休暇 | 7日 |
| 通院休暇 | 妊娠中又は出産後1年以内の女性職員が医師等の保健指導又は健康診査を受ける場合に取得できる休暇 | ~妊娠満23週:4週間に1日 ~妊娠満35週:2週間に1日 ~出産:1週間に1日 ~出産後1年:1日 |
| 出産休暇 | 女性職員が出産する場合に取得できる休暇 | 出産予定日前8週間 出産後8週間 |
| 出産補助休暇 | 配偶者等が出産をする場合に取得できる休暇 | 3日 |
| 短期介護休暇 | 親族で2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の世話をする場合に取得できる休暇 | 5日 要介護者が2人以上の場合は10日 |
| 介護休暇 | 親族で2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の世話をする場合に取得できる休暇 | 3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(無給) |
| 介護時間 | 親族で2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の世話をする場合に取得できる休暇 | 3年の期間内において、1日につき2時間を超えない範囲内(無給) |
| ドナー休暇 | 骨髄移植の骨髄液提供のため検査又は入院する場合に取得できる休暇 | 必要と認められる日数 |
| ボランティア休暇 | 報酬を得ないで社会貢献活動(災害支援活動等)を行う場合に取得できる休暇 | 5日 |
※上記は令和8年1月1日現在における休暇制度です。
子育てに関する休暇等
| 休暇名 | 概要 | 日数 |
|---|---|---|
| 育児休業 | 3歳未満の子等を養育する場合に取得できる休業制度 | 養育する子等が3歳に達する日まで |
| 部分休業 | 小学校就学前の子等を養育する場合に取得できる休業制度 | 1日2時間以内または1年度につき 77時間30分(無給) |
| 子育て部分休暇 | 小学校等に就学している子等を養育する場合に取得できる休暇 | 1日2時間以内または1年度につき 77時間30分(無給) |
| 育児時間 | 生後1歳に達しない子等を育てる場合に取得できる休暇 | 1日2回各30分 |
| 看護等休暇 | 職員の子(満12歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)が負傷し、又は疾病にかかった場合等に取得できる休暇 | 5日 子が2人以上の場合は10日 |
| 育児参加休暇 | 配偶者等が出産の日以後1年の期間(小学生までの上の子がいる場合は出産予定日の8週間前から出産の日以後1年の期間まで)に取得できる休暇 | 7日 |
※上記は令和8年1月1日現在における休暇制度です。
主な勤務地
・豊中市役所(中桜塚3丁目1番1号)
・千里文化センター「コラボ」(新千里東町1丁目2番2号)
・庄内コラボセンター「ショコラ」(庄内幸町4丁目29番1号)
・豊中市上下水道局(北桜塚4丁目11番18号)
・市立豊中病院(柴原町4丁目14番1号)
・豊中市伊丹市クリーンランド(原田西町2丁目2番1号)
※上記は一例です。上記以外の勤務地に配属される場合があります。また、国、府、民間企業等への派遣など、市域を超えて勤務する場合があります。
柔軟な働き方
時差出勤制度
時差出勤制度とは、公務の運営に支障が生じない場合に1日の勤務時間(7時間45分)を変更せず出勤時間を繰り上げ、又は繰り下げて、出退勤前後のプライベートの時間を確保し、ワークライフバランスを支援するための制度です。豊中市では、標準の勤務時間以外に、下記8パターンの取得が可能です。
| 勤務開始 | 勤務終了 | |
|---|---|---|
| パターン① | 7:45 | 16:15 |
| パターン② | 8:00 | 16:30 |
| パターン③ | 8:15 | 16:45 |
| パターン④ | 8:30 | 17:00 |
| 標準の勤務時間 | 8:45 | 17:15 |
| パターン⑤ | 9:00 | 17:30 |
| パターン⑥ | 9:15 | 17:45 |
| パターン⑦ | 9:30 | 18:00 |
| パターン⑧ | 9:45 | 18:15 |
テレワーク
豊中市では、業務や生活環境に応じて柔軟な働き方の実現のため、週2日を限度としてテレワークを導入しています。通勤時間や移動時間を短縮するとともに、時差出勤や休暇と組み合わせることで、家族との時間やプライベートの時間を充実させることも可能です。
福利厚生
各種給付金
入院費補助金、育児支援金や育児支援金等、各種給金を支給します。
健康管理
健康診断の実施のほか、人間ドックや健診等にかかった費用の助成を行っています。
資格等取得助成制度
定められた資格等の取得にかかった費用の半額を助成します。(上限あり)
電話による健康相談事業
24時間・年中無休で電話による健康相談受付サービスを実施します。
人材育成
キャリア形成
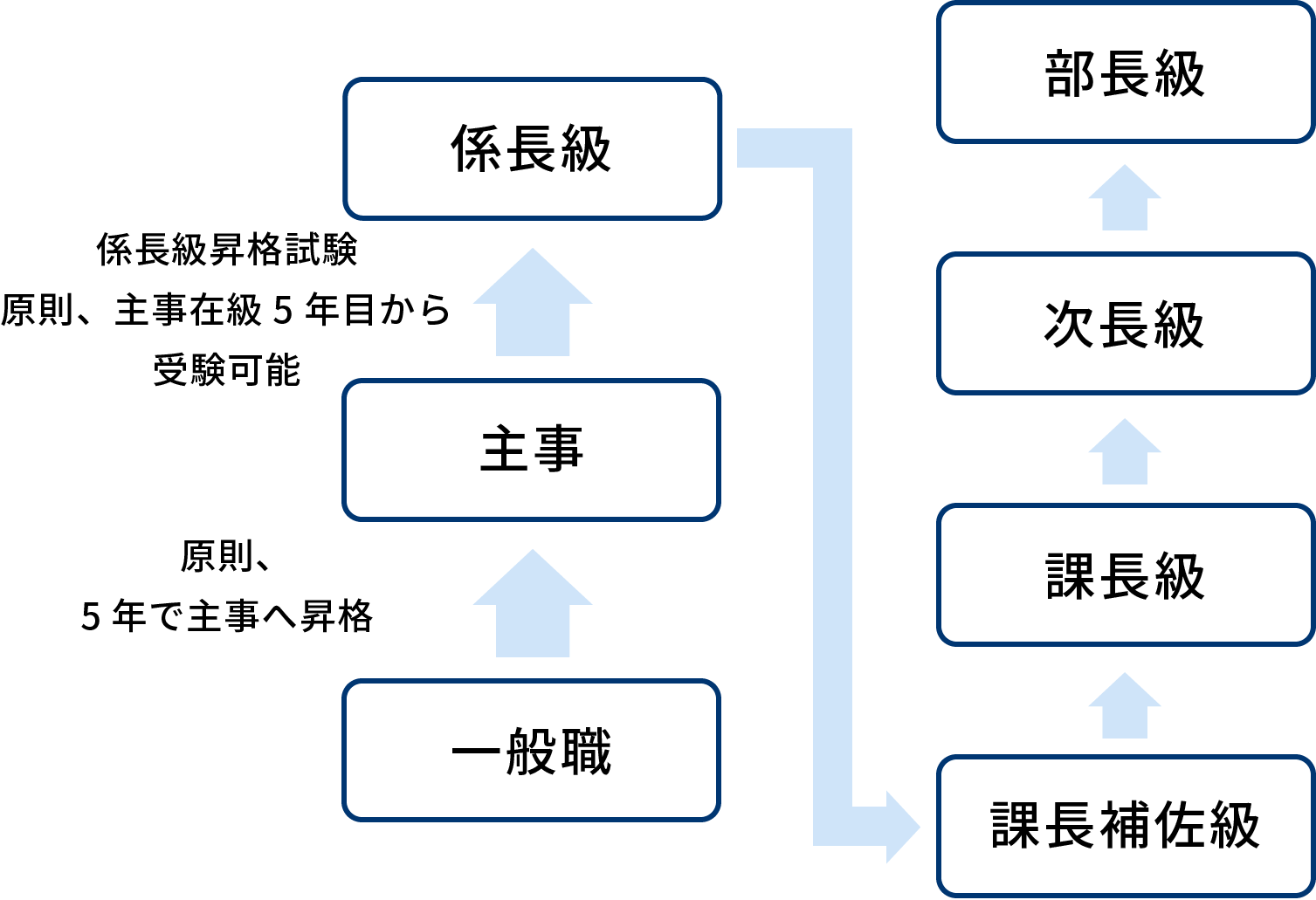
ジョブローテーション制度
若手職員の能力開発を目的とし、採用から一定年数以内に複数の職場を経験してもらうための制度です。
原則、事務職は採用から3~5年経過後、技術職・社会福祉職は採用から3~7年経過後に人事異動の対象となります。ジョブローテーション終了後は、原則5年以上同じ部署で勤務した場合に人事異動の対象となります。
職員異動希望調査
職員の意向の把握を十分に行い、能力開発を目的とした適材適所の配置換えを行うこと等によって、職員の多様な特性や能力を積極的に引き出します。在課5年以上の職員の次年度4月1日の定期人事異動について、異動希望の有無及び希望する部署等の意向を提出することができるものです。
人材交流制度
民間企業や他団体へ職員を派遣することにより、新たな価値や考え方を取り入れ、より良いサービスを創り出していくための人材を育成することを目的としています。
主な実績:大阪ガスマーケティング株式会社、ANA大阪空港株式会社、公益社団法人2025年日本国際博覧会協会、総務省、厚生労働省、経済産業省、山形市、尼崎市、西宮市、沖縄市 等
人事評価制度
人事評価は、職務目標の達成に向けた努力の過程を振り返り、職員がその職務を遂行するにあたり発揮した能力および挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価であり、職員の育成に繋げることを目的として実施しています。また、人事評価の結果を、昇任・昇格を含む人事異動や、昇給および勤勉手当へ反映しています。
研修制度
職階別研修
| 研修名 | 内容 |
|---|---|
| 新規採用職員研修 | 社会人、公務員としての自覚や使命感、仕事のための基礎的な接遇・マナー、業務遂行に関する基礎的知識を学びます。 |
| 2年目職員研修 | ボランティア活動等を体験するとともに、地域の現状や課題等を学びます。 |
| 3年目職員研修 | 地域の現状に触れながら、「市民視点」と「自律・共創の視点」を高めるとともに、行動力や主体性の源となる経験を積みます。 |
| 5年目職員研修 | 政策形成の意義・目的、政策課題の把握・分析・設定方法等の理論と実態を学びます。 |
| 係長級・技能長昇格前研修 | 係長級に期待する役割を遂行するうえで、必要な心構え、知識等への理解を深め、昇格後の職務に対する意欲を高めます。 |
| 新任係長級研修 | 係長級職員としての業務管理、部下・育成等の知識やスキルを学びます。また、部下等及び自身のメンタルヘルスへの配慮について、知識やスキルを学びます。 |
| 新任課長補佐級研修 | 所属の副統括者として求められる役割・責務を認識し、組織運営(連携、業務分担等)、人材育成等の基本的な知識、スキルを学びます。 |
| 新任課長級研修 | 統括者に求められる役割・責務を認識し、組織・職場のマネジメントに関する制度やしくみ、市政の現状・課題を学びます。また、部下のラインケア及び自身のセルフケアに対する認識・理解、管理職員としての心構え、知識・スキルを学びます。 |
| 自己啓発休業制度 | 公務を取り巻く社会環境の変化に対応できるよう、職員としての身分は保持したまま、職員に自発性や自主性を生かした幅広い能力開発や国際協力の機会を提供することを目的に休業できる制度です。※取得要件あり (1) 大学等における修学のための休業 2 年(特に必要な場合 3 年) (2) 国際貢献活動のための休業 3 年 |
職場外研修
各職場で求められる能力や専門的な知識、技術の習得のために、研修専門機関や他団体が実施する研修情報の提供、旅費等の支援やその他研修専門機関・先進自治体等への派遣支援を実施しています。
育成責任者・担当者制度
新規採用職員には、配属後の各職場で、研修を受講した育成責任者および育成担当者が配置されます。育成担当者は、新規採用職員にとって一番身近な相談役になるとともに、新規採用職員が1年間に身に着けるべきことを明確にしたうえで、その計画や経過等を新規採用職員本人と共有しながら指導をしていきます。
資格取得支援
本制度の要綱に定める資格等の取得に要した経費の全額または一部を助成します。また、資格等の取得に要した日時について、職務に専念する義務を免除します。
修学部分休業制度
職務能力向上を目的に、学校教育法に定める短期大学・大学・大学院・高等専門学校等の教育施設に通学するために、1週間19時間以内で取得できます。(無給)
※上記額は令和8年1月1日現在における金額です。
※経験等に応じて前歴加算あり。